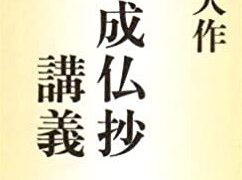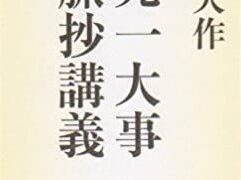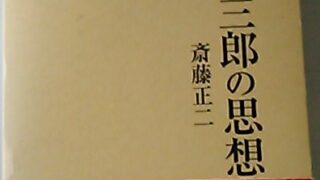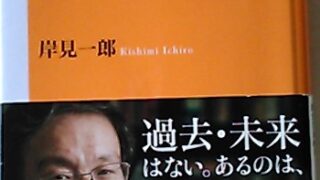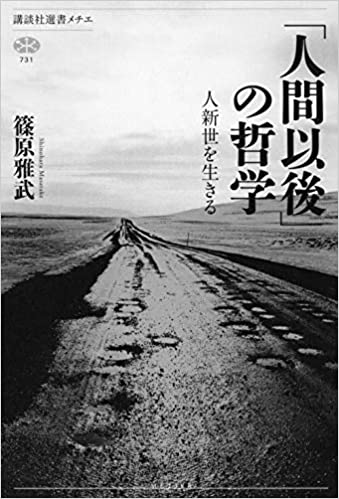「人新世を生きる」
篠原雅武 著
はじめに
人間から遠のく世界・人間不在の世界に向かう、自然な秩序からも区別される
人為的秩序そのものから遠のくだけでなくそのコントロールを外れてしまうものへと変容しつつあるのを目の当たりにしている。(脆くて定まらぬもの)
地球温暖化、人新世、パンデミックの脅威、AIの深化、内戦による国家の崩壊といった難題が浮上する。
・三つの課題
- 「脆さと定まらなさ」という実存感覚
- 「人新世」の学説(人間の条件の哲学的な再設定のための指針)
- 「生活世界」(人間的尺度を外れた世界)とそれを取り巻く「事物の世界」
との差異に関心を向ける生き方
重要なのは、人間を唯生き延びさせるだけでなく、生気あるある人間にするもの、人間として生かすものとしての実存的な条件を新たに発案する事である。
・モートンの云う「存在するためにはものは“脆く、繊細”でなければならない」これらの議論は人間ならざるものの世界との接触面においてある状態を指す。「人間以後」を問うことは、人間がどのようなものとして生きるのかを問うことを意味している。
「プロローグ」2019年、8・3
人間世界は、自然世界のちっぽけな一部でしかないと捉える事が求められているのだが、科学文明のおかげで生活は便利になった反面、自然世界に取り巻かれた無残なその現実に無感覚になっているようだ。
「世界の終わりは、ハイパーオブジェクトの浸食により引き起こされる」
ワットの蒸気機関から始まり、マンハッタン計画(1945年)と広島長崎への原爆投下で加速され二酸化炭素と核物質の人為的増加は地球の在り方のみならず人間世界の在り方を変えていく。ものはただ定まらないというだけでなく、消えてしまうものとして存在する。メイヤスーのいう人間の思考の外側に常に何かが存在する」そしてその思考は全く偶然的である「思弁的実在論」
・美的領域としての歌
雪の脆さにおいて存在させるオーロラの歌
事物が互いに触発するのはそれらの事物の手前にある奇妙な領域(痕跡と足跡)美的な領域である。定まらぬものが崩壊し消滅していく後に残される“残り香”のようなものが漂う領域である。
第1章、世界の終わり?
「人間から離れた世界」
世界は必ずしも人間によって生きられるとは限らない。
人間によって生きられる家は、生気を刻み込むことで辛うじて死の噴出を抑えている。湧き立つような生命を持つと同時に腐敗し、暖かいと同時に悪臭を放つものである。(多木浩二)家はメンテナンスを必要とする人工物である。
・「人新世」における居住可能性問題
人間は今や地球システムを変え、プロセスとその構成要素を脅かしていく。
世界の終わりは人新世であり近代的な世界像の終わりでもある。
表面では全てが許され、人は普通に時には不真面目に生きるという氷河期が来ているとも語られる。従来と違うものになったエコロジカルな自然危機は、単なる危機を意味するだけではなく、人は依然として人間中心的立場に捉われている限りにおいては生活条件の実在的危機であり崩壊でもある。
・定まらなさの中で生きる
エコロジカルな危機(人新世、温暖化、海面上昇、異常気象、パンデミック等)
「平家物語」の“盛者必衰”「方丈記」の“ゆく川の流れは”「奥の細道」における“流浪への願望”そして“枯れかじけた”宗祇の「さび」の精神
進歩とは異なる崩壊と消滅の過程
・生を超えた力(非人間的)、それは感覚可能で現実的な物質にある非有機的な力(あたかも凍りついた死滅の風景が思い浮かぶ)
第2章、世界形成の原理 (ガブエルとメイヤスー)
「公共圏」という世界像
社会や文化といった領域の中で生き、思考し、議論するとき何らかの価値観イデオロギー、観点といったものに立脚し自らのよって立つ信念として絶対的に正しいものとして保持してしまっている。刺激に満たされた疑似的公共空間(感覚麻痺の世界から一時的に正気になれるとされる逃避の世界)
言語を持ち文化に生きる人間は、ほとんど運命的に生の自然から疎外されて生きているとも評される。重要なのは、社会的文化的の共有である。議論し承認し差異を認め多文化を認めることを通じて共有を模索される。又一面において、シャンタル・ムフは合意形成の場と考えることに反対し、「敵対的な公共空間の創出」と捉える。
世界の不安定化現象(温暖化、パンデミック、集中豪雨、台風、津波による水没といった出来事)これらは人間世界を支えてきた思想的設定そのものが壊れかけていると考えた方がいい。現実のシステム設定そのものの不安定化と考えることも出来よう。根本的な変化それは人間的尺度を離れたところで起きている。ここで重要なのは、従来の世界像の崩壊を認めることだ。
“事実は存在せず、解釈だけが存在する”これはニーチエの言である。
この原理は、何であれ望むことを云ったり、行なったりするのを正当化するものとして現れた。テクノロジカルに改変された都市環境は、人工的なものであり本物と虚像とが混在している環境である。都市建設は、土地利用を変化させ、プラスチック製品の増大は海洋汚染を引き起こし、今や世界は人間の尺度、理解といったものから離れたところで存在する。
何億年もの時間と資本主義としてのせいぜい500年の時間の間での相克。
・人間から離れた世界とは、言語によって共有される人間的な公共領域とは無関係に存在する。通常の常識にとらわれている限り知覚困難であるようだ。
人間が定めた尺度に従わせることのできない側面、すなわち人間が生きてる事に先立って存在する人間的でない側面を指す。
・カントがその存在を示唆した知識以前のものとは、主観的自我を離れた客観的世界、歴史的世界として現実に存在しており人間はこの世界に属し出入りしている。又自然界以外にも歴史的芸術、宗教の世界など種々の世界があるとも西田幾多郎は主張している。(種々の世界)
・死体への変化以前に生きていたはずのその人の個性は痕跡として世に刻まれ宇宙の始源や地球における生命の発生、人類の始源など、人間の個性を主観的自我を離れたところにある世界において見定めようとする(西田)
死において人は一方では無個性の物体として葬られ(土に埋められるか火に焼かれるか海に沈められていく。だが他方では歴史的実在としては各々が一あって二なき個性を持った実在であったことが理解される。
・写真を媒質とする「原風景の層」としての作品世界(感覚的意味において)
第3章、人間から解放された世界 (テイモシー・モートン)
「人間的尺度を超えた時空」
宇宙の一部として人間を捉えるのは、人間中心的な思考に捉われている状態を抜け出すヒントとなる。
・形なき形
形なきものの形を見、声なき物の声を聞く(形相を有となし形成を善とする)
・存在の不安
世界の不確かさ、危うさ、はかなさ、脆さへの感覚から生じるもの。
・オンラインの世界の成立
・マルクスの「経済学批判」
政治、文化、宗教といった領域を上部構造と捉え経済的生産様式(資本主義的)を下部組織として存在させいずれ共産主義的な生産様式を現実のものとすることを求めたが、マルクス亡きあと共産党宣言にある如くその思考そのものが現実世界から遊離した新型イデオロギーとして政治組織化し独裁化して現在に君臨している。
・「自然なきエコロジー」
グルーバルゼーションに対抗するローカルな場所
私がいるこの場所は、人間的尺度を外れて安全でなく不安定なものへと変容しつつある。(消しゴムの山)
・2010年代半ば以降、夏温度が上昇(豪雨被害は世界化してきている)
2018年2019年の集中豪雨、台風豪雨各地に甚大な被害をもたらしている。
2011年の大地震と津波による被害は忘れることが出来ない。
第4章、人間以後の哲学 (グレアム・ハーマン )
「公共圏」から遠く離れての
・感覚的な媒質の客体性 ~ 経験する人間に先立つ所に形成される
・同上における相互作用 ~ 個々の人間的生の実践的な世界(自己中心的)
人は物体として存在し生き延びようとするのだが、いずれ消滅していく。
「確かに生きていた」としか言いようがない。無数の痕跡が刻み込まれた地上としての世界に私達は住んでいる。事物の中で自分自身になり自分の自己同一性を保つことになる。それ故に光や雰囲気、暖かさといったものは独占出来ないもので私に属するのではないという。
第5章、人間の覚醒 (柄谷行人)
人間がいてもいなくても存在するものとして世界を考えると、人間の生、人間の経験の形式を規定し左右してくるものとして世界を捉えることになる。
視点の食い違いを巡る柄谷の思考において重要なのは、カントの哲学である。
人間生活の条件を新たに構想するには人間に先立つ所にある世界の物質性、事物性、音響性、客観性を強調し世界設定に関わる思考を試みることである。
・カントの「コペルニクス的転回」
天動説を地動説に転回させた(主観中心的思考を否定)
・「鏡と写真装置」
鏡の映る見慣れた顔(左右が逆)と写真の写る私の顔どっちが本当の顔なのか
・カントの他者性を認める「物自体」
「超越論的態度」とは、我々が意識しないような経験に先行する形式を明るみに出すことである。従来の「人文学」では、人間にとって正義や倫理が重要だったがそれは人間中心の価値観である。
・デジタルな日常世界と荒廃していく現実世界
新たな環境学で人間の消滅を考えることに、果たして何の意味があるのか。
第6章、地下世界へ (フレッド・モーテン)
人間世界に対する外部として逃げ場としてすでに存在している。人間世界から放りだされた者たちの集まるところとしてすでに存在している。
地球的事物が西洋哲学では無視されてきた。これらをいかに感じ、表現するかが今問われている。
・音響と平滑空間
声(きわめて個性的なものとして)音響(生活世界の外部に広がる)
平滑空間は触覚的音響的な空間 ~ 風、雪、砂、氷などは人間の意識とは相関しない(聴かれ触れられての領域)
・自然世界から切り離されて成り立つ人間の生活世界が破綻して廃墟に移り変わる。
・はかない音響性
機械的に記録された音(レコード、カセットテープ、ICレコーダー、マイク)
電子音楽、テレビが発する音声と映像が生活の場に入り込む。テレビが存在していることの根本とは機械が世界を対象化し、客観化し人間的なものとして手なずけコントロールするための手段にされている。
・マサオ・ミヨシの「建築の外部」論考
ポストモダン建築への批判として、ありふれた日常の建物をその外の空間に連れ出す「建築を開く」~ 窓の形を調整し、内部と外部の相互性を確保し庭と街路の共有スペースを考慮する。
・建築の再物質化 ~「街路で遊ぶ子供たち」日常の普通さを取り戻す。
・「逃避」について
自分自身のものでない空間と構造において起こる逃避の諸形態。
関係性の拒否ともいえるが存在感の肯定とも受け取れる。その意味では周囲からの無関係の孤立状態に自らを追い込むことではない。
・ボーダレスな世界~ロス、ニユーヨーク、東京、香港、ベルリン、ロンドン
得体のしれない人たちが住み着くところとしての都市世界
第7章、新しい人間の条件 (アーレントからチャクラバルテイ)へ
・アーレントの思考の意義の限界(人新世における人間の条件)
人間生活を支えてきた環境条件が悪化し限界にきている今日、人間が存在し生きていくための条件の基礎となる価値観を新たに発案する事である。
過去においてスプートニクの打ち上げ時地球を離脱してゆく事の第一歩と称賛したアーレント達。
・生活世界と事物の世界との差異、隔たりは自然の事物から切り離された人為的制作物である。
・「人間の条件」における根本的変化
これらの諸条件には自然な事物と同様の条件づける力が備わっている。
・地球は人間の条件の本質そのものである。それは宇宙における独自のものであり地球という自然が人間を条件づけるものであることを認め、人間の生気に欠かせぬものとして君臨している。アーレントは世界の二重性には気づいていたが、それを理論化できなかった。
・西田幾多郎の「矛盾的自己同一」~ 生命論
生命の世界と歴史的世界 ~ 生き生きとした生命の場としての世界
人間存在を条件づけるものとならない限りにおいて事物(人為的)は互いに無関係のものの寄せ集めでしかなく、つまりは非世界である。
地質的なものと道徳的なものが連動して動く時代。あえて言うなら“人間の尺度”を超えた人間ならざる世界の存在に気づかされている。事物は地下世界に住み着いているが生活世界においてあからさまに露骨に表れる。
・世界「ケアの倫理」
これら事物としての制作物は生活を支えるためのものだが他方では自然世界に対する有無を言わせぬ介入でもある。人間にとって必要とする素材を取り出し、作り変え地球的自然性を消滅させている。人間世界と地球世界の接触としての鉱物資源(鉄鉱石、大理石)石油、ガスといった天然の地下資源
エピローグ
脆さ、定まらなさの感覚(ある種の虚しさ)は人間不在の所、人間以後のものとして考えざるを得ないものに変わりつつあるがゆえに生じていると考えることが出来るであろう。ここで重要なのは人間がなお生きていくうえで何が大切になるのか何が求められるのかを問うことである。主体性の喪失と思考停止、想像力の欠如を特質とする集団的没個性状態が優勢になっていく状況下において災害やウイルスの発生はあくまでも世界の変化に気づくためのきっかけでしかないと捉え、何がリアルかを巡る感性と思考の在り方さらには思想、言葉の立て直しが迫られようとしている。
・ミヨシの日本認識は、より現実主義的な政治的分析がその基礎にあり、西洋及び他のアジア諸国との政治的な関係性に規定されている。従来からの近代主義的な排外性や封建制、狂言性を結びつけたような代物ではない。又現代の日本の言語文化においてはその質素で貧困化すらしているとする。そこに君臨するものはトークショーや漫画本であり、座談会、パネルデスカッションの類である。この発生源は文化の退行現象と西洋依存という二通リの現象における絶対的矛盾のなかに映る。
・「ハーバーマスの統制的理念」~全てを包括する統一された世界など存在しないとする(ハーバーマス)の考えは誤りである。人間が立ち去り不在になっても地球は存続する。惑星に基礎を置く全体性に着目して人間の条件を考える。
惑星の中には、別の種類の生命が存在することになるだろう。微生物、アリやネズミ、ゴキブリといった生命、生命が続く限り別の種類の進化のサイクルが存続するだろう。人間的なものとして定まり得ると考えられてきた世界は、気候変動、海面上昇、干ばつ、パンデミックと共に崩壊するのは確実だ。
とはいえ、たとえ壊れたとしても私たちはまだ生きている。
定まり得ると考えられてきた世界などあっさり崩壊し得ることを知ってしまった私たちは、空いた穴から様々なものが入り込んでくるのを感じているのだから別に怖れることはない。
以上