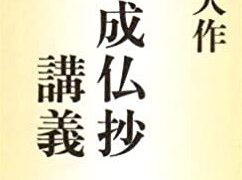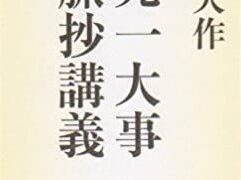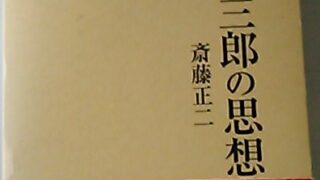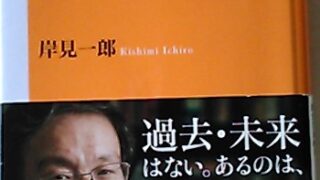吉川英治 著
・「庶民は水、政治は器」政道さえ公明ならば水は器の中の平和に住む事を好む。
細かい政網など立てるより迅速に明らかに庶民に安心を与えることだ。
安心は“信頼”であり、決して政道の賢人(聖賢)や水も漏らさぬ手腕家でもない。そういう人では間に合わない乱世であり信じられる人によって安心を求めたいのである。
こんな時勢に施す政治などというものは実に難しい。
誰がやっても同じと人は言うだろう。しかしその反対に今ほどやり易い時はないともいう。民心は乱脈から統一に至るを望んでいる。
国家の大道を知る限りにおいては、大義大道の為と服従一致を望むものだ。
出る人物が出さえすればだが。庶民の力だけではなし得ないことを庶民の心に成り代わってやってくれる待望の人物の出現が待ち望まれる。
尚「名分」のない戦いは勝てない。さりとて、敵でもなし、味方でもなし尊敬はしなければならないが尊敬のみでは陥れられる。形に表れたものよりは形を見せない幻の敵(両面の将軍;ここでは秀吉と家康)世の中のどういうものが戦いを興し、何のためにしているのか。「義もあまり過ぎたるは邪義とか」
熱し過ぎず冷淡過ぎず(近すぎず遠すぎず)
“笛吹けど踊らず”時の潮を妨げる利己心の亡者ども。そんなことは誰もが言う常識というものだ。山門の腐敗堕落は嘆かれながら幾人もそれを改めることが出来ずに今日へ来てしまった。
・「叡山は天台、石山は門徒」、宗派は違うが仏徒に変わりはない。愚民から献上させた財を持って城郭のような石垣や山門を築き銃槍を蓄えている。
・実はこれは殿(信長)の発意ではござらぬ、さすればいかなる悪名も藤吉郎が負います。(自身はそう決意いたしておりますので)
・八百年来安住してきた特権の下に今もなお時代の変遷を見縊ていた錯覚も大きい。
この“特権と信仰の砦”に対して(宝塔・伽藍)蹂躙することは為し得まい。
・自分の値踏みを知らないで知識的であって、室町文化から少しも出ていない。
・あっても無いような「将軍家」という代物が国家の枢要なところに名だけを持って存在している時代感覚ほど怖ろしいものはない。
・己の好みによって同じ型の人物ばかり揃え、一律に見ること信玄は大嫌いである。小我な欲望は届きそうな事でも得て届かないが、忠節から迸る真心ならどんな至難な事でも貫かれるものである。
・大将たる資格
高い教養と位置と権力の外に庶民の実体がよくわかっている者でなければならない。文化人であるとともに野生人でもあることが必要であり純粋すぎる文化人でもいけないし純然たる野生だけでも成就しない。
・脾肉の漢(劉備玄徳)腿の肉を削る如く痩せる脆弱な文化や爛熟過ぎた治世には逞しい野生を配することが生命力を復活する一つの方法(人材の苗床)
本来の政治とは、人間の職能として最高の善治を奉行するものでなければならない。あたら卑しい私欲の徒の看板のように地に堕してしまったのは明治末期から大正、昭和かけての事である。
・大臣高官は威重く、入るにも出るにも常に燦爛とあってほしいものだ。如才のない鼻息ばかりうかがっている輩などはいつの世でも民衆は見ていたくないものだ。何をして遊んでもそれに溺れない自己を持つことだ。
・関が原に於ける光成の「挑戦の機構(巨いなる企て)」
当時260万石の徳川勢に対する豊臣政権存続への反体制
秀吉生前時には、家康は副社長の座にあった。秀吉亡き後、前田利家も去り、すんなりと新社長の登場となるべき状況にあった。ところが石田三成(平取締役)が異を唱え「関が原」という大プロジェクトを構想し“天下分け目の戦い”をデザインした。強さの魅力だけを売り物にして(弱さの強さ)を理解しないで力任せに押し切ろうとする戦国武将の悲喜こもごも
・本来、利害には二種類あり①物質的利害②地位や立場上の利害、共に争いごとの起因となるもので厄介である。
・他人の真実を握った者が勝者となり、自分の真実を握られた者は敗者となる。
世間の目から見えぬ隠された(真実)というものが存在する。
・財務の名匠たることは、戦陣の名匠たる以上に人間として難しいもので死でも先があるという生命の無限を信じればこそ猶の事。
・これからの大事は、第一に新しい軍備の充実、戦法の改革なお時代に遅れない心がけが肝要となる。
戦国の諸将はあえて勤王というような言を平常はそう用いなかったようだ。
・匹夫の出世ほど危ないものはないぞ。人の嫉み、あげつらい、みな己が慢心すればこそ、嫉妬は女だけのものではない、いや男性のそれは女性のように色に出さないだけになお怖れていい。
・疚しさのない真実の力は微笑の裡にも十分相手を圧してくる。俗諺にも“仏者”のウソを「方便」と云い“武門”の変を「戦略」という。
・総じて戦国初頭から群雄割拠し始めた各地の豪勇英傑の間には、私業のみあって世業はなかった。況や国業とまで理想し自覚している程な者は殆んどいなかったと云っていい。日本を考えるにも、日本だけしか考えられない狭量と狭量がこの中で角遂し私業の争いを幾度にも繰り返してきた。群雄割拠がそれであった。もう今日に至っては意義も理由もなくむしろ障害だ。
・敵に武門の節義を売ろうとする者にはその人間だけの小理屈と打算ある。
・人は軍略の才のみ知って経済的頭脳はあまり認めない。鉄砲、火薬、望遠鏡、医薬品、皮革、染め物類、日用什器、~医学、天文、軍事けれどなぜか「宗教と教育」を絶対に嫌った。
・欧州使節の人選に上った方々は、16歳を頭に九州の大藩の子弟であった。
・強気が悪いわけではない。強気は心の瓶に満々と蓄えておくべきものである。
けれどそれには絶対に軌を誤らない文化的な省察と一見弱気にも似ている沈着な力の堅持が必要、みだりな強がりは正しい相手を威嚇できないでむしろ逆効果を生んでしまう。(この主君があるからは)という絶対な安全感を持たせて自分に頼らせ切った和と中心への信頼だった。
・勝頼と信長とを並び立たせた今の時代が無情なのである。あなたは(勝頼)
信長の敵ではない。信長は朝廷を忘れず奉公人を以って武門自身の本分としている。源平以後の武門の割拠的存在を皇室中心に徐々と是正しまた自ら臣下としてのその範を現に示している信長というものの大きく中央にある今日となっては~何事につけ朝廷を尊び朝廷を中心にして統治を成す主義の信長には地方の侍や士族とておのずから心を惹かれ、一地方の主に過ぎぬ武門の主人に対してはつい離れるともなく心入れの違ってくるのは是非もない成り行きであり(自然に期するが如きものでしょう)この世の千年もの歴史では、信長も今覇を誇るとも散らぬ桜やあらん、燃えぬ覇城や有るべきや。
・どこまでも裸になれぬ漢、可愛げのないヤツ、なぜ愚痴の1つもこぼさないのか、ちと目の前に滞りすぎておる。なぜ先行きの大利を考えん。商売として立っても男児の仕事は大いにあろうが知れたものではないか。国、城の主となるとは大変趣が違う働きがいが違う男と生まれた生涯の幅もちがってくる。
・滅亡に終わるものは大概な場合、外敵よりも内的にその素因がある。
人身の弱点(私欲、私憤、私闘)といった醜いものばかりを助成するような形態の下では当然瓦解するものだ。内部に禍の根のない限りは外敵も乗ずることは出来ないはずだ。
・古来火攻めを以って攻城に成功したためしは幾多もあるが水攻めを以って功を遂げた例は殆んどない。
・秀吉が求めているのは単なる案ではなく具体的な数字と誤りのない設計の確証である。信長には壮大な計画と理想に伴う実行力があった。その反対に信長から家康を観るに自分にはない奢らない、誇らない、かりそめにも摩擦を起こさない「分」を知って「野望」を表さずその内に蓄え、同盟国に危うさを気負わせない辛抱ずよく困苦に耐えるという特徴を持っていることを認めていた。
・人間の真理を察し人生を批判することなどにかけて普通人以上な目を備えている「光秀」の事である。~かくして光秀の心理にとっては、刻一刻と魔となり人に回り、菩提となり又羅刹となり正邪二道の岐路に右遷か左遷かと夜も日にも懊悩し続けていたものに間違いはないだろう。
・饗応役の恥を軍令上の中にまで及ぼし、明智家の不面目を戦陣にまで晒さ縷々苛酷なお仕打ちというしかない。必定領土替えが行われてやがて坂本四郡
「蘭丸」に下されるであろうなどという風説の出所も、格下げの意志をみんなが敏感に読み取って~何にしても心外千万無念というも言い足りぬ。
・身、武門に育ち男として土岐源氏の血を受けながら、信長ずれの駆使に身を屈め生涯を終わろうや ~ “汝には読めぬか、信長の腹黒さが”
・あれも人間だから怒ればこれくらいなことはやるだろうとは思っていた。それにつけても自分の油断は笑うべき一代の失策だった。
・信長の勤王ぶりは、人心収攬の一策であり、政治的にそれに努めたものであるなどと評している者があるが ~ これらは時の司権者の策であり、理知の略でありとする利口者の見解であり、日本の臣民、大衆には君臣一つの流れもなくそれによる情念も無しとするびやっけんにすぎない。
・“閑話休題”(作者の駄説を許されたい)
戦国期の武門の人々を指して、国家観念の欠如を云い真の勤王はない統一のための方便であり、政治的仕組みの上に為したもので、封建的種々の道義のみだとなす説が強い~「室町期」に於ける皇室への仕えの怠りは言語道断ではあるが、信長以後の黎明期の時人は国家間をすでに呼び戻していた事を自分は信じて疑わないものである。
・誰がそんなややこしい理論高説に耳を貸そう。「名分」とは民の直情に合致するものだ。大義とは民の中に持っている鉄則の信条だ。この標的を無くしては、戦も政治もうまく運ぶわけがない。「日向守」がかりそめにも逆と呼ばれる旗を持っては例えどれほど努力してももう先は見え透いている。要するに日向守の「逆事」は治世に疲れた智者の破綻である。
・医者の眼から見れば織田もない明智もない等しき領民にしか見えん。
「太平記」の中にも楠木正行が“渡辺橋の合戦”の折、足利の大軍を討って河中に溺れんとする足利の兵を救い上げておる一条がある。
一言に言えば光秀はあの賢才を抱きながらいつの間にか立った一つの美徳(謙虚さ)を心に失っていたと云えよう。それは彼が務めてきた教養の結果で
本質ではなかった。知性の人にはままある姿だ。
我らが謙虚さを討ち捨ててよい時とは敵陣へかけ入るときだけだ。(家康の言)
・すでに己に敗れている者が何で外に勝てるか。況や世を統べてまとめ上げることなど出来るわけはあるまい。
・その痛哀をして天下の悲愁たらしめず天下の慶祝とさせなければならない。
とすれば、小義や私情を乗り越えた信念がいかほど自己のうちに硬くあってもである。不用意に表しては誤解されやすい。統帥の死はやはり三軍の喪であり、しかも彼の臣なり、犬死とさせてはならない
・それは一つに天意なりというしかない。人は人を相手として戦いあくまでも人と人との戦場を描いているが、偉大なる宇宙の士気も加わっているのである。
尋常に天意を抱かず、人力を尽くして神意に通ぜざる三軍であっては、いかに誇るとも「人間の陣」にすぎない、「神人」の陣には打ち克てない。
・僧たるものは、人の範ともならなければその道も行われぬ。世人から見て命惜しみの人かなと笑われては桑門の道も教えも廃りになる。
・さてさて又なき御武運にお会い為されましたもの哉、人の一生も生涯の士道もその仕上げは良くも悪くも死によって定まるとか申しますが、今日の御生涯は現し身の人も生かしまたご自身の一命をも末代に生かす晴れの一期お喜び申されずに居られませぬ武門にも「敵の喪を討たず」という古言もあるよし。
・“大道は心源に徹す五十五年の夢覚め来れば一元に帰す”
・人間の想像力にはおよそどうしても一定の限界がある。後でその“非”に気づくことでも事実の現れる瞬間まではいつも十目十指的な常識の線から一歩も出られないのが普通らしい。けれど古来身を以って歴史を描いた日本武士の姿は常におのずから最高の劇的一天地を作っている。湊川、四条河原、桶狭間、川中島、高松城の一舟、松の間の廊下、雪の夜の本所松坂町「劇以上の劇」
・かかる重器は、持つべき人が持つ間こそその人のものなれ、決して私のものではなく、天下のもの世々の宝と信じます。~その名器名刀がやがて誰の所有になろうと左様なことは、「光春」の知ったことではありません。
「戦乱による時の勝者」にとっても悪質な闇の横行者や怠け者にも当時の農村は良い隠れ家にされていた。帰郷者や外来者と祖先以来そこに住み土のみに天命を託して五穀を耕している百姓とは当然区別して考えなければならない。
・「清須会議」に列したほどのものは次代の一流級ぞろいである。ここに加わってはいないが北越の陣の前田利家と佐々成正、別格に徳川家康とを加えて日本の中心的人物は網羅されている。
・“自分を小さくしてはならない”我欲一点を観られてもならない。多数が可とする以上はやはり順応せねば却って後に悪かろう。
・「離」~ 尚早、妄想、執着、疑惑、早急、一切白紙の心となる
・智を弄するものは智におぼれる折角の“機”をも逸する。
・「勝家」は以前から策略家と見られ陰謀に富むかの如く定評されているが、事実は正直者であった。その勇、その謀もその正直さもみな勝家の特徴として巧みに使いこなし北陸探題の重任、多くの将士をも又広大な領土をも授けて十分な信頼を持ちかけていたのは信長がよく見抜いていたからでもある。
・本来戦は彼の本技ではない。しかし「戦は経綸の車軸」であることを知り、いかなる大理想をかざそうと戦に敗れてはいかんせん。彼は戦に対しては、絶対に賭けし権化となって戦いきるのであった。
・よいことをする人間を見ると、何か悪いけちをつけたがる。正しく働く者に対して、卑屈な働かぬものが何のかのとあげつらう。いつの世にもあることだ。
大きく世の変動しているときは特に清濁の飛沫も激しい。
・信長は主君である。どこまでもその性格に沿い従い日常も呼吸を合わせ大道一巻の歩みを揃えていたのは当たり前である。が既にその人亡き今日、何で先人の規炬に捉わるるであろうや。
・世を見る眼、全ての思想も以前の彼にあらず我にあらず真の“刎頸の友”というものはやはり艱苦の中で知り合ったものでなければ生涯を契られまい。
・信長亡き後武門の一将一将人間と人間という対比に帰って接してみると依然と大分違ってこないわけにはゆかない。
・とかく人に喧嘩をやらせてみたがる世間にも、~どんな乱麻と暗澹を呈してる時流の中でも必ずどこかに特異な人物はいるものだ。
・三項一約 ~ 「和と婚と分領」
・凡の興るところ人あり、人の興るところ上にありという
・巨きな山は近ずくほど巨きさが見えなくなる。山懐に入ると尚解らなくなるものだ~大概は山の全体を見ていっているのではなく~本当の人物というものは中々いるものではない。到底そんな狭い眼で見通せるような者だったら、所詮ある程度求めれば世間に代わりのいくらもある人物でしかあるまい。
・「心耳と機眼」
吹鳴の合図を果たしながら猶その中に陣気がなければならない。進むに死を超えしめ、退くに乱れなきよう。耳のある将は螺声を聞いてその兵の怯勇を知るという。なお「心耳」のある名将となると、いかに上手が吹いても、敵の詐を見破り虚実を察し鋭鈍を量り決してその耳を詐くことは出来ないという。
では“心の耳”とは? ~ 「教外別伝」に附すしかない(茶や禅に)
茶人の使う銅鑼の音 ~ 客は主の一打一打に身を澄まして心で音を聞く。
ドラには南蛮、朝鮮、明、和作種々あるが民土興隆時の製と衰退期の製とでは、いかに音が美わしくても余韻は違う。陽と陰、一般の歌調音楽も民の士気を導くものとされている。疎かにできない。
・“機を掴む”とは常識に過ぎないが、事ある日の大機、小機を平然と見逃してゆくのもその常識の病であると云えよう。
非常識を策として敗れ去るのではなく、多くは常識を辿って常識に敗れ終わるのである。
・戦場における死生の間を通らずには、一個の人としての成長もなく、戦場に学ばずしては武門の子の教学もなく、平日机座の学問から受けたものではない。
・柴田勝家の主陣地たる中尾山
・敵の弱質な部面に病菌を植え敵の内臓を内より食い破るのが「謀」の目的なり。
・“謀は利を以って計る”(古来からの常例)
古来内応醜反の徒が利に走りながら利を得て生涯を栄えた試しのないのもまた不思議である。これだけは巧くゆくだろうと自身の場合だけ例外として見、しかも勝利に帰すことまでを強いて信じている。驚くべき妄動である。
・兵法「九ッの付目」
相=切=粉=位 体=隙=疑=弛 用=起=居付=尽
・捨身の将士と私憤の領民との一結しがたいものを、苦も無く一縄に結わいてこれを鼓舞する。後は天の計らいに任すそれしかあるまい。
人の小智の及ばぬところ、天祐とは要するに大いなる天運に順うことで天の運行に逆らう事でない。
・異体脆弱なものをあえて内容に許していたという根本的な誤謬を冒していた。
・平俗の間で“位が効く”“効かない”と言われる“位”という言葉。
軍容、陣気、静動、外交、政治でもこれが物を言う範囲は大きい。
ここでいう“位”の意味合いは、位階勲位などのそれとは違う。
・民に道義を立てるには、示すに情義の政治を以ってせねばならない。情義を法に持つためには、温情美賞主義のみが決して策を得たものではない。時には峻烈無情にも似る厳科の断刀も又下さねばなるまい。
・“死中生あり、生中生なし”~ 勝たねば死のみ
・貧しい日こそ人を作る。殊に女の教養は貧苦窮乏の冬日を超えてきた風雪の薫香でなければ誠に根のない切り花のそれにも等しい。
・“下手な打ち手は休むに似たり”~“位押しと肚芸”の兼ねあい
眼の付け所が違う ~“藍より出でて藍より青し”~ 我以外皆師也」
彼が学んだ人は、一人信長ばかりではない。どんな凡下なものでもつまらなさそうなものからでも自分より勝る何かを見出してそれを我が物としてきた。
智は広く天下の智を集めていた。
自分を非凡なりとは自信していたが、賢者なりとは思っていない。
・割普請制の特徴は、俺の領分、俺の時間を持つことであって、そこには日雇い根性にはない自己への試しが表されてくる。本気でやればどのくらい働きが出来るか、“やればこんなもんだ”という自信を持ち、誇りも生じて魂も入り面白さも涌き、職人的道義も上がってくる。元よりこの請負制は凡愚の利己心を活用したものだが、小我に始まり無我に入り利に始まって利を見ざる境地に人を動かすこれを悪いと云えようか。人が道を求め聖賢の語を求めるのも仏心を興して菩提を求めるのも一つの利己心とされるならば社会万般、人間凡愚の働く活泉には悉く不純ありということにもなる。
・たぎり立った茶の湯をやる。~ 何事にも“ぬるいこと”が嫌いなのである。
・主君が家来を養ってきたのではなく家来が主君を育ててきたというのが徳川家の独自の醸成である。
・世上の説というものは、その根を正すとおおむね他愛のないものです。
世間はやはりそのようなことを、有り得ぬこととはせずに有りそうな事と考えているのでしょうか。
・人類がしてきたことは、何千年も同じことを繰り返してきた。古くから哲人は何度も言ってきた。“何と人間は愚かであることか”
・「三つの本能」 ; ① 飲食即是道 ② 淫欲即是道 ③ 闘争即是道
・秀吉を指して強いて事を構え旧主の遺子を除いて信長公の後を襲わんとする乱臣というという非難を世上にばら撒いている。道義や節操が必ずしも大きくものをいう世でもないが、さりとて人間の善美の性や真実の姿が全く枯れはてた世とも思われない。
・“天下分け目”というが、二つの天下なら二つのまま何とか折り合いはつかぬものか。つきそうなものではないか。世間をそう考える、人間悉く平和を希ていないものはない戦を呪っていることは確かなのだ。それでいてひるまない
勢力分布が二つになっても、却って従来の恐怖よりも天下総がかりと犠牲を思わせる。これは人間のせいではない、人間がやるとすれば人間ほど愚かな動物はないということになる。では何が、何ものがそれをやるというのか個人ではない、人間の結合したものがやるのだといえる。
人間と人間とが群れをなし、万、億と結合したものは最早人間ではなく地上の群生動物にすぎない。これを人間と見做し人間的解釈に拠ろうとするから解らなくなるのではないか。過去現在を通観してくると、世の中が人間の意志だけで動いてきたと思うのは錯覚であって、人間以外の宇宙の意志といったようなものが多分にあるとは云えないだろうか。
・時の代表者になった者はもう純粋なる一人間とは呼べない。姓名官職はすべて皆これ単なる仮の符牒でしかない。その正体は沢山な人間の中のやはり一つの生命体に過ぎないのである。だが彼は庶民の望む平和への権化でもある。
だから相反するものに逢えば両者は忽ち戦争に入り外交の秘策も敢然と行う。
無数の人間(あるがままな人間の姿が闘争、貪欲の本能、犠牲、責任、仁愛の精神を飛躍させ時には文化の飛躍をも示すという不思議を天性の世にも見せているのである。
秀吉はゆらい、戦は最後の手段也、外交こそ戦であるという信条である。だが外交のための外交ではない、外交あっての軍力でもない。常に軍力あっての外交なのだ。軍威軍容を万全に備えてからものをいうのである。
・思想的にも一方は秀吉に賛し、一方は家康の名分に共鳴し、同じ一族の中でも骨肉が別れて相戦うという。
・禅家では、人相よりも肩相を尊ぶ。威ありげに反りかえっても、肘を張っても肩相から見るとだめらしい。反り身では三千大世界を懐に入れてもはいらん、対立し突っ張りあうらしい。不思議な人間の行為、相寄り部落を作り社会の形を持ってからついにその禍の大を又愚かさも知性に解りきっていながらなおやめにやめられないで凄まじい宿業の修羅、この中に戦国の武者ばらはいかに生きいかによくこの宿業を果さんかと哀れにも命を奪い合うのである。
名を美しく、潔く、そして犬死ならぬ人間の死を忠と呼び義と呼び信と呼ぶ当時の道義に結びつけて、仆れるとも頬に微笑を持とうと希うのであった。
・「器」ばかりは生まれついた量を急に大きくさせようとしてもどうにもならぬ。
・故信長公は物事に固着せぬお方であった。万象は常に生々流転して動いて居るそれを人間はつい動かぬもの動かしがたい現実と考えて固着する、悪い病だとおっしゃっていた。戦は博打ではない。これだけのものをどう転ぶか出る目のしれぬ運命に賭けてよいものか。運命が自分を恵んできたときのみに手を出して掴めばよい。(家康はよく自分を知る者であった。)
・「恩」ということ、しかも自身が施したものでもない父の徳望を御曹司が少し過大に思い過ぎている。しかもその人その勢威が実存している感すら思いを意識し、意識させる行為は非常に危険なものであるにかかわらず、世間知らずのこの名門の子(信雄)は今でも世間に通用するものと極めているらしい。
・一つの革新期を跨ぐには必然な区分けだが、人間個々の心理には時の自然力に対する不平と反発を素直に享受しきれないものだ。血気や短気は青臭い若者だけの通性でなく、初老にかかる老人こそ危ない短気の持ち主でもある。それは生理的にも自制と反省が弱まる頃だし一つには焦りや負けん気に駆られがちだからとも云えよう。
・「芸術の野は無限」
上手いものを食べたい、良い女子を持ちたい、良い屋敷に住みたい、名声をあげたい、人によく言われたい。そうした欲望を仕事の張り合いに持つがよい。
その平凡を卒業した後の欲の事を云ったまでだ。
・失敗もしてみなければ人生の険路は解りません。失敗の反省こそその人間に重厚な味と深みを加えてゆくので、天の恩寵だと思わねばなりません。
・敵国に有らぬ流説を蒔いてその結束を破るという手段は古今東西変わりはない。(内紛と内訌の訴因を植える)
・義によって起こった戦の公言がおかしなものになってしまう。
家康の立場は第二義に置くがいい、偽和であろうがなんであろうと平和に対して不平を鳴らす理由はどこにもない天下万民の喜びと共に家康も心より重畳に存じています
・名門の出には、自己主義者が多い。周囲のものは皆自分のために存在しているという錯覚、自己が他人のために尽くすなどは思いも及ばぬことだった。
・この男はすぐ本気になる、自己の正直さをガンガン行って額の青筋にその証明を描いて見せるというたちの外相を好む正直者だ(佐々成正)
「弱まる」とは「強がらぬこと」~「二股もの」と蔑まれたがよろしい。
・自分の命すら粗雑に考えている人間が、何で他人の命など愛せよう、又どうして無数の命の上に立って政治を取り世を立て直すなどという資格があろうものか。さも誠意らしい言葉の裏に、実は相手に要領を掴ませず、巧みに自己をぼかしてしまうのが家康のよくやる奥の手なのである。
およそ時運に逆らってはよくその一生を得た人間が古来からいない事を家康は知っていた。人間の小と時の偉大さを弁えてその時を得た人間に抗すべくもないことを原則にすべて考慮し又秀吉に一歩も二歩も譲っていた。
・闘争術策の世界には常に担ぎ屋が立ち回っている。担ぎ上げて自己の志望を遂げようとする。春秋以後、世には接客という職能さえあって、遊説向きの弁舌家が必ず幾人か抱えられている。
家康病む、危篤、死すとまで話は大きくしかも真しやかに伝えられている。
・越後の上杉景勝、特徴は謙信以来の士風あって剛健と素朴、又あえて他を冒さず他からも冒されるを許さず。独自の保守性にあった。
・「根来衆と高野衆」とは昔から犬とサル
一山に本物の僧さえいればいかに荒廃の法燈でも再び蘇るものだと木食上人は身を持って僧衆に教えた。
・羽柴の名の由来 ~ 丹羽、柴田
「分別者の分別すぎ」~丹羽長秀彼は自己の尽くしたことは、秀吉の為ではなく、清須会議に、信長の正嗣(三法師)を唯守り育てるに有った。
(自己を劉備玄徳に孤児を託された諸葛孔明になぞらえて)
・男性の本音(好色家の秀吉)
美貌では松野丸、心映えと肌の綺麗さでは加賀の局、上臈風の知性美と気品の高さは三条の局である。これらは肉愛の花々。しかし情愛の真心では、一番に女房(面と向かって言うとつけ上がるから逆の表現を用いる)第一の恋人は母、おふくろ、姉はおふくろのお供え物として不憫な奴と思いやっている。
・孔明の「天下三分の計」もダメでした。天下二分では激しい対立を呈します。理由は猜疑とそれに乗ずる策謀家、野望家、不平家共の扇動、そして人間本来の飽くなき欲望事態だと宗教家はいうでしょう。
・両雄並び立たずですが、敵亡き国は亡ぶの譬えもある~革命とは終止的な言葉ではなく前の革命を革命し次の革命を約束するものである。
もし人の一生がその多岐なる迷いと多難なる戦いもなく淡々たる平地を歩くようなものであったなら、何と退屈なすぐ諦めてしまうようなもの、人生とは苦難苦闘の連続、あえて人生の快味と云えば、打ち勝ったわずかな間の休息のみにあると言っていい。だから苦難を怖れない人にのみ凱歌と祝宴が齎されると言っていい、逆に苦難に弱い迷いに弱い負けやすい人にのみ悲劇は続く。
・将軍職名は頼朝このかた源氏系の者に限るが慣例になっている。
「征夷大将軍」この度は「関白」豊臣を設ける・四姓(源平藤橘、)打破
・「五奉行」(文官制)~前田、増田、浅野、石田、長束
・「真田幸村」
春秋の世の慣い、一個一個の私的な恩怨など生涯持ってはいられません。
不満は時代に暗い“井の中の蛙たち”の独善的な強がりである。大阪軽視、狭小な反秀吉の危険思想にある、是こそやがては徳川家を誤らすものでなくて何であろう。
以上